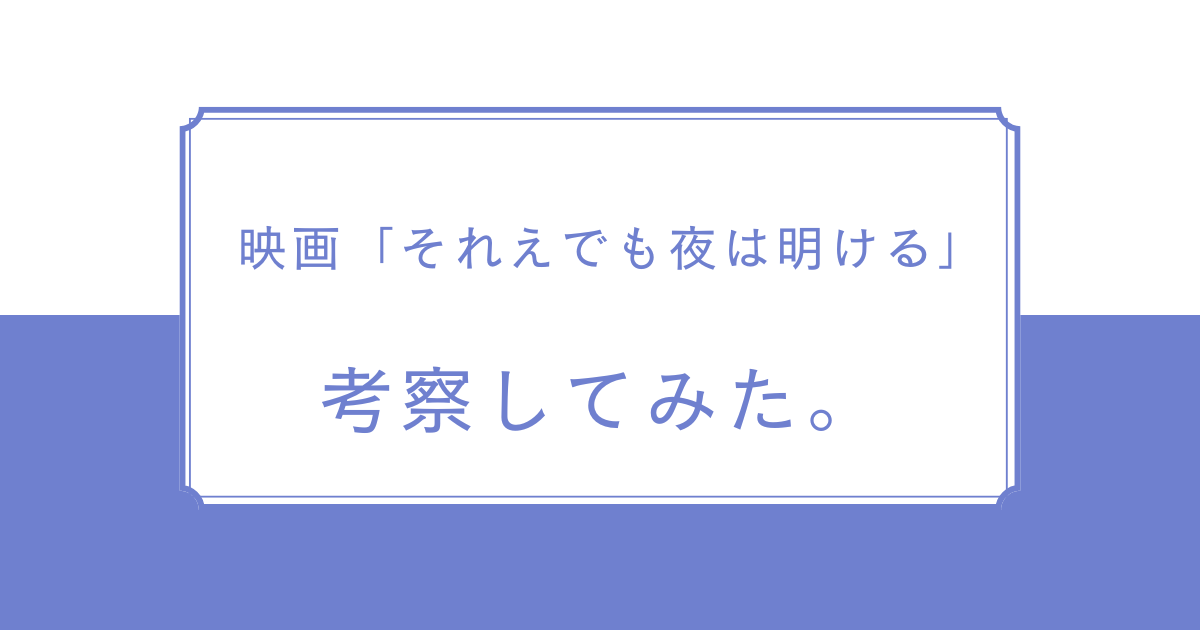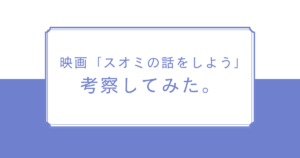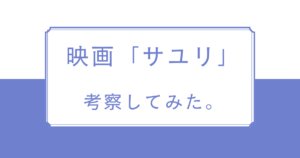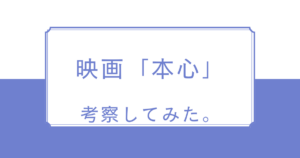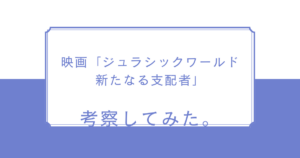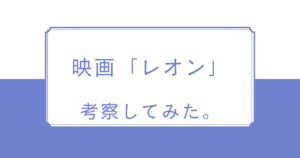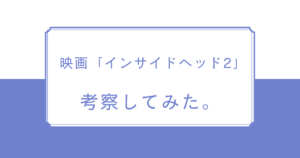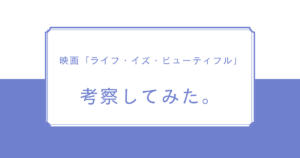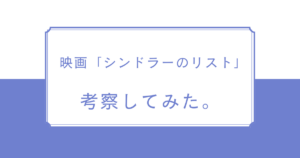映画「それでも夜は明ける」は、強烈なリアリティと重厚なメッセージ性を持つ作品です。
この映画は、誘拐され奴隷として売られたソロモン・ノーサップの実話を描いています。
彼の壮絶な12年間の体験を通じ、人間の尊厳や不正義に対する怒りが表現されています。
ここでは、本作の重要なテーマや描写についての考察を3つのポイントに分けてご紹介します。
考察①: 社会の歪みと奴隷制度
本作で中心に描かれるのは、奴隷制度という社会の歪みです。
ソロモンは本来自由な人間でありながら、突然その自由を奪われてしまいます。
この状況自体が異常であり、また彼が何を言っても信じてもらえない絶望感が見る者に強い印象を与えます。
奴隷制度は、南北戦争の遥か前からアメリカに存在し、この映画ではその残忍さが具体的に描かれています。
奴隷市場で裸にされ、親子が引き離されていくシーンは、その非人道性を表わしています。
この歴史的背景を知ることで、作品のメッセージがより深く心に残るでしょう。
考察②: 黒人奴隷の視点と白人社会
映画のもう一つの重要な点は、黒人奴隷の視点から白人社会を見ることです。
主人公のソロモンは、白人社会で受け入れられず、孤立無援の状態に置かれます。
彼の体験を通じて、見る者は奴隷制の理不尽さとその時代の社会の矛盾に気付かされます。
特に、主人公を取り巻く白人たちの態度が示すのは、彼ら自身がどれほど偽善的であるかということです。
例えば、ベネディクト・カンバーバッチ演じる奴隷主は、奴隷制に疑問を抱きつつも声を上げられないといった消極的な態度を見せます。
これは、良心と社会に対する妥協の間で揺れる人々の心理を象徴しています。
考察③: 信仰との逆説的な関係
この映画では、人間の信仰が持つ逆説的な力も描かれています。
奴隷主であるエップスのように、聖書を信じながら同時に非人間的な行為をする人物描写には心を痛みます。
彼は聖書の言葉を振りかざしますが、黒人が人間でないと信じることで、自分の罪悪感を隠そうとしています。
この自己矛盾は、南部社会そのものが抱える大きな問題を暗示しています。
聖書やキリスト教的価値観に基づく正義と、それを利用して行われた奴隷制の悪行の対比によって、観客は深く考えさせられます。
まとめ
「それでも夜は明ける」は、深い考察を必要とする映画です。
奴隷制という歴史的背景を通じて、人間社会の根本的な問題を鋭く問いかけています。
この作品によって、観る者は人間性や社会の在り方について改めて考える機会を得るでしょう。
重いテーマではありますが、その中に宿る強いメッセージは、今の時代にも多くの示唆を与えてくれるものです。