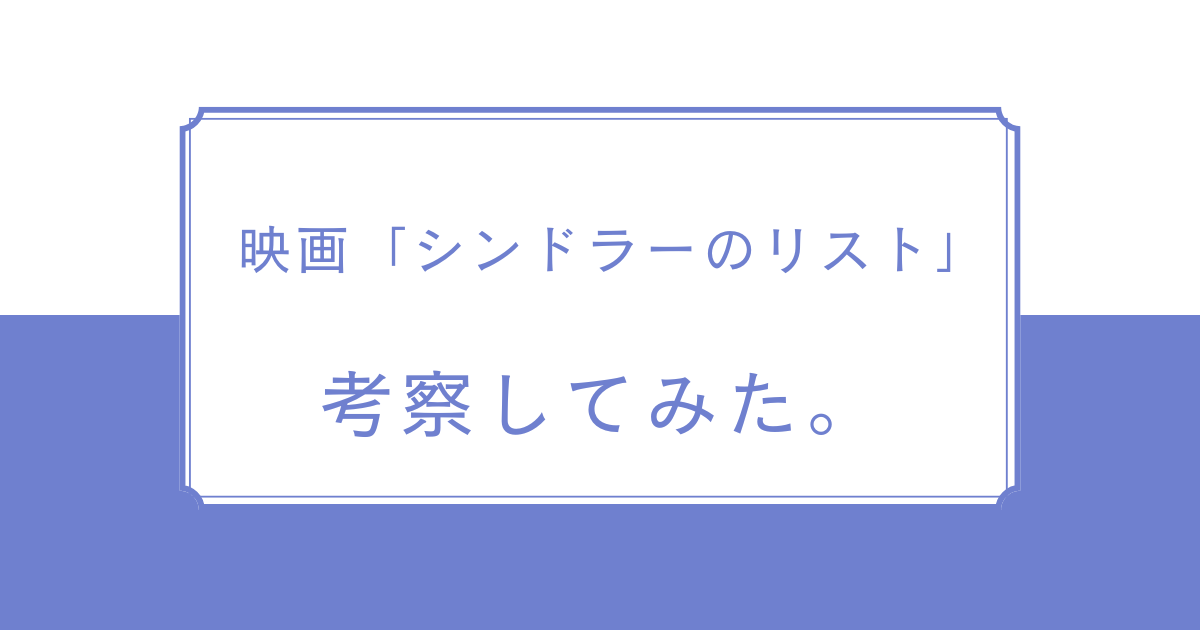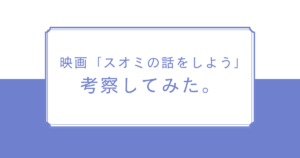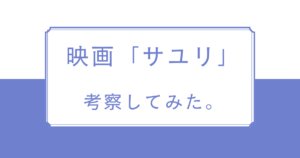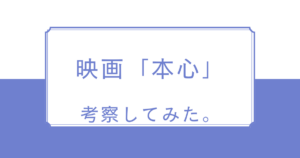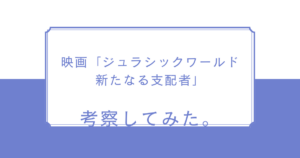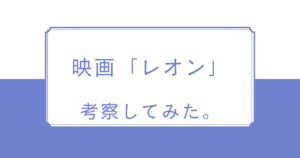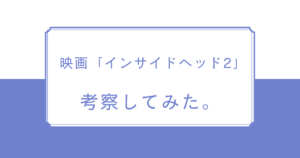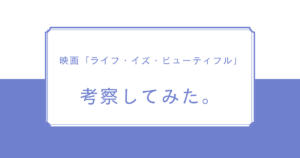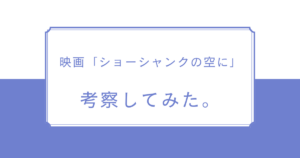映画「シンドラーのリスト」は、スティーブン・スピルバーグ監督によるホロコーストを描いた作品で、多くの人々に深い感動と共感を呼び起こしました。
そのテーマと描写の重厚さから、鑑賞すること自体が一種の試練となるといわれることもあります。
今回は、この作品を3つの考察ポイントに分けて深掘りします。
考察①: スピルバーグの個人的な使命
「シンドラーのリスト」は、スティーブン・スピルバーグ監督が長年温めてきたプロジェクトであり、彼のユダヤ人としてのルーツが強く反映された作品です。
監督は、この映画を制作するにあたり、アカデミー賞などの映画賞のためではなく、個人的な使命感に基づいて取り組んだとされています。
その背景には、ホロコーストに関する正しい認識を広めたいという意図がありました。
具体的には、ユダヤ人の歴史や文化、そして彼らが直面した過酷な現実を、多くの人々に知ってもらうための作品として本作が位置づけられています。
スピルバーグはそのために、映画の制作から得た報酬を受け取らず、シューヴァ財団を設立し、ホロコースト生存者の証言を記録するプロジェクトに資金を投入しました。
「シンドラーのリスト」は、単なる娯楽映画ではなく、教育的使命を果たそうとするスピルバーグ自身の姿勢を如実に表しています。
考察②: ビジュアルスタイルとその効果
この映画を語る上で欠かせないのが、その特異なビジュアルスタイルです。
「シンドラーのリスト」はモノクロで撮影され、これが歴史的なドキュメンタリーとしてのリアリティを強調しています。
通常、映画はカラーで撮影されますが、本作では意図的にモノクロが選ばれました。
その理由として、当時の記録映像に雰囲気を近づけることや、感情をより直接的に伝えることを狙ったと言えます。
劇中に登場する赤いコートの少女のシーンは唯一のカラフルな場面であり、その鮮烈さから観客に強烈な印象を残します。
このように、モノクロを基本としながらも時折カラーを使用することで、重要なメッセージの伝達を効果的に行っています。
この大胆な演出によって、観客に直接的な感情を抱かせることに成功しています。
考察③: 歴史の再現とフィクションの境界
「シンドラーのリスト」は、史実を元にした映画ですが、全てが実際にあったそのままを描いているわけではありません。
スピルバーグは、映画におけるストーリーテリングの観点から、一部の場面やキャラクターにドラマチックなアレンジを加えています。
例えば、ラルフ・ファインズが演じたアーモンド・ゲートなどのキャラクターは、史実に基づきながらも映画的な劇的効果を持たせるための演出が施されています。
こうしたフィクションの要素が史実と相まって、映画を一層強烈なものにしています。
しかし、このような改変には批判もあり、史実としてのリアリティを損なうのではないかという声もあります。
それにも関わらず、この作品が後の映画やホロコーストに関する議論に与えた影響は計り知れないものがあります。
映画は作品としての完璧さだけでなく、教育的・歴史的価値を提供することに成功していると言えるでしょう。
まとめ
「シンドラーのリスト」は、スティーブン・スピルバーグ監督が自らの使命として取り組んだ作品であり、その制作背景やビジュアルスタイル、史実とフィクションの融合が観客に多くの考察の機会を与えます。
この映画は、単なるエンターテインメントにとどまらず、歴史と向き合い、未来に対する教訓を伝える重要な役割を果たしています。
観る者にとって、この作品は重いテーマを扱っているだけに、何度も考えさせられるものであり、その意義は極めて深いと言えるでしょう。