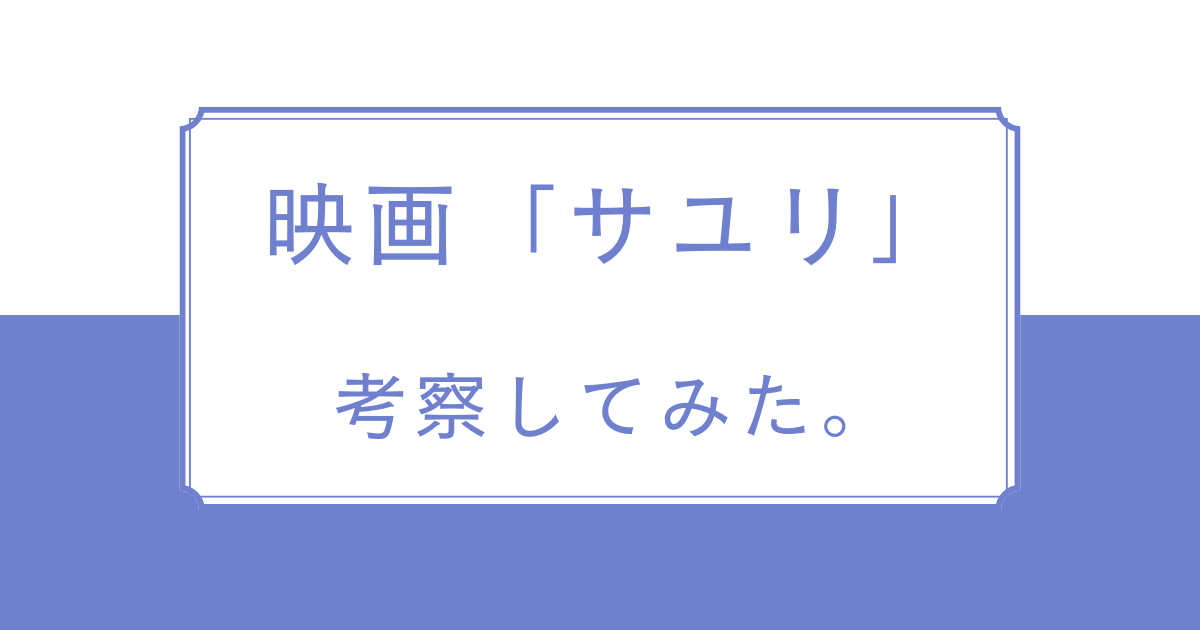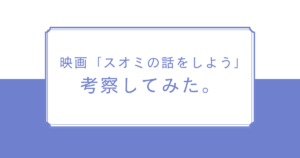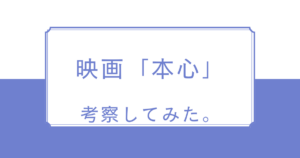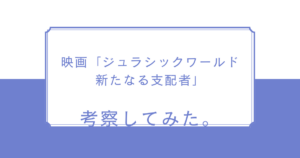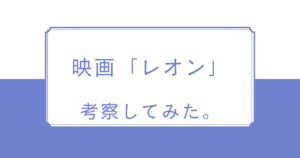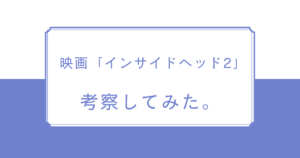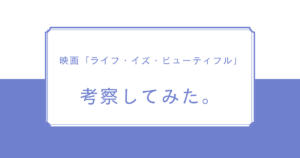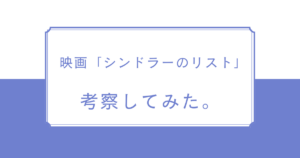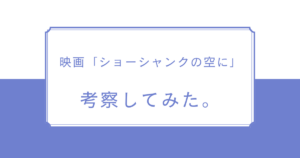映画「サユリ」(原題:Memoirs of a Geisha)は、日本の伝統文化である「芸者」をテーマに、西洋的な視点で描かれた話題作です。
美しい映像美や物語の展開が特徴のこの映画ですが、文化的な視点やキャラクター描写についてさまざまな議論が交わされています。
本記事では、映画「サユリ」をより深く理解するための3つの考察を紹介します。
考察① 「芸者」とは何か
映画「サユリ」は、芸者の世界を題材にしていますが、その描写には西洋的解釈が色濃く反映されています。
これは映画の文化的背景と制作意図を考える上で重要なポイントです。
物語では、芸者はしばしば「日本版の娼婦」と誤解される表現が見られます。
実際には、芸者は伝統芸能を担う職業であり、舞踊や音楽、会話術など高い教養が求められます。
映画がこれらを十分に描き切れていない部分は、日本文化を知らない観客にも誤解を与えやすい点として議論の的になっています。
一方で、芸者を「神秘的で美しい存在」として描いた映画のビジュアル表現は、観客に強い印象を残しました。
特に、芸者たちが見せる舞踊のシーンや和装の美しさは、作品の魅力の一つとして評価されています。
このように、「芸者」の定義や役割についての誤解と正しい理解が交錯している点は、映画「サユリ」を考察する際の重要な切り口といえるでしょう。
考察② 主人公・サユリの描かれ方
サユリ(千代)は、幼少期の貧困から芸者として成功するまでの道のりを描かれたキャラクターです。
彼女の成長物語は多くの観客を引きつけましたが、同時に彼女の描かれ方にはいくつかの批評が寄せられています。
まず、サユリが「運命に翻弄される女性」として描かれている点が挙げられます。
物語の多くが彼女の恋愛や苦難を中心に進行しており、自己決定的な要素が少ないと感じる人もいるでしょう。
このような描写は、女性キャラクターの主体性を欠いているという批判につながることがあります。
一方で、サユリの内面的な葛藤や努力は、観客に感情移入を促します。
特に、彼女が芸者として成功するために努力を重ねる姿や、尊敬する人物への一途な思いは、多くの人の共感を呼びました。
サユリの描かれ方は、彼女自身の物語だけでなく、芸者という職業や日本の文化的背景をどのように伝えるかという点でも興味深いテーマです。
考察③ 日本文化の再解釈
映画「サユリ」は、ハリウッドによる日本文化の再解釈の典型例とも言えます。
そのため、日本国内外で異なる評価を受けています。
映画では、京都の町並みや四季折々の風景が美しく描かれていますが、これらはあくまで西洋的な視点から見た「日本のイメージ」に基づいています。
例えば、実際の伝統芸能や習慣と異なる部分も多く、これが日本人観客にとっては不自然に映る場合があります。
しかし、こうした再解釈は、西洋の観客にとっては「異国の魅力」を感じさせる効果があります。
特に、日本文化に馴染みのない人々にとって、この映画は芸者の世界や日本の伝統美を知るきっかけとなりました。
一方で、こうした文化の再解釈がステレオタイプの強化につながるリスクも指摘されています。
そのため、この映画を鑑賞する際には、制作意図や観点の違いを踏まえて楽しむことが求められるでしょう。
まとめ
映画「サユリ」は、その映像美や物語で多くの人を魅了しつつも、日本文化の描写やキャラクターの設定についてさまざまな意見が寄せられる作品です。
芸者という存在への理解や主人公サユリの成長物語、西洋的視点による日本文化の再解釈など、多角的な視点から楽しむことができます。
この映画は単なる娯楽作品としてだけでなく、日本文化と西洋的視点の交差点にある作品として、深く考察する価値があると言えるでしょう。