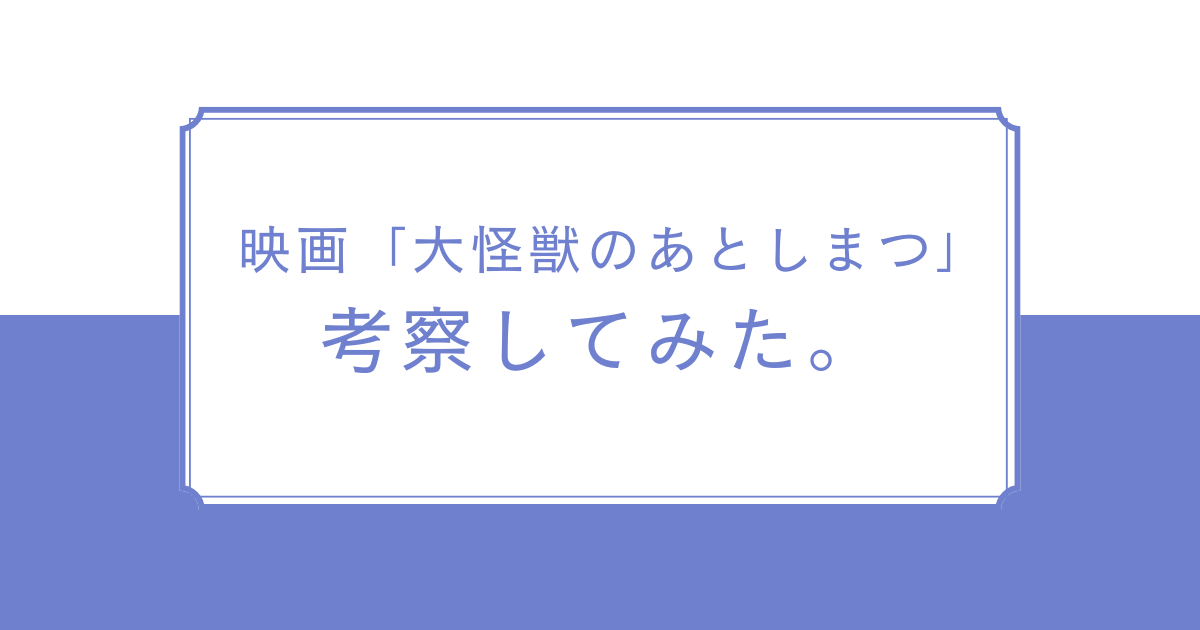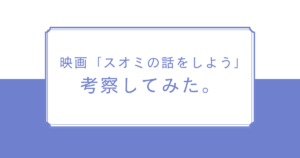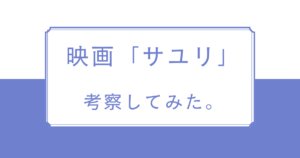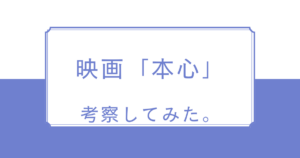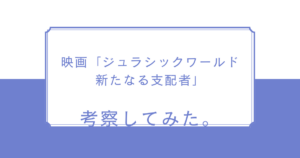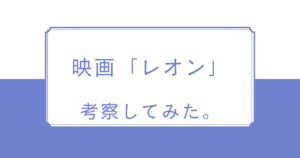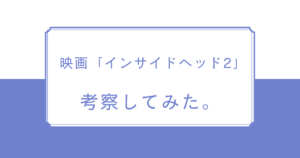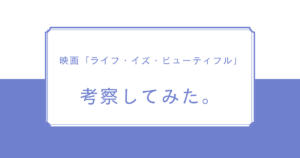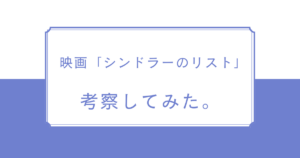映画「大怪獣のあとしまつ」は、従来の怪獣映画とは異なる視点で描かれた作品です。
「もし、巨大怪獣が倒された後の処理をどうするか?」というユニークなテーマを掘り下げています。
本記事では、この映画の深層に迫り、考察を3つの観点から展開していきます。
考察① 怪獣映画の新しい可能性
本作は、「怪獣映画」のジャンルを再定義する挑戦を試みています。
従来の怪獣映画は、怪獣との激闘や人類の勝利に焦点を当てることが一般的でした。
しかし、この作品は怪獣を倒した後の「後始末」という側面をテーマに据えています。
例えば、映画では巨大怪獣の死骸が残され、腐敗や環境への影響といった問題が描かれます。
これにより、怪獣という存在が単なるフィクションではなく、現実社会の課題を象徴する存在として浮かび上がります。
従来の「破壊と再生」の物語に終始せず、「その後の現実」を描くことで、観客に新しい視点を提供しています。
こうしたアプローチは、怪獣映画の可能性を広げる意欲的な試みと言えるでしょう。
考察② 社会風刺としての側面
映画には、現代社会への風刺が随所に込められています。
特に、怪獣の処理を巡る政府の対応や、メディアの扱い方は、実際の災害対応を思わせる描写です。
例えば、映画内では、処理にかかる莫大な費用や責任の所在が議論されるシーンがあります。
これらは現実社会における大規模な問題、例えば原発事故や環境汚染への対処を暗に示していると言えます。
また、登場人物たちが権力争いや利害関係に囚われる姿は、危機的状況における人間の弱さを浮き彫りにしています。
こうしたリアリティのある描写により、物語は単なるエンターテインメント以上の深みを持つ作品へと昇華されています。
考察③ エンターテインメントとしての課題
一方で、映画としての完成度に対する評価は賛否が分かれる点も注目すべきです。
ユニークなテーマ設定に比べ、物語のテンポやキャラクター描写には改善の余地があると感じられる部分もあります。
例えば、主人公たちの行動や感情が十分に掘り下げられず、観客が共感しにくい場面が見受けられます。
また、コメディ的な要素とシリアスなテーマのバランスが取れず、全体のトーンが不安定になる瞬間もあります。
このような課題は、テーマそのものの魅力を十分に活かしきれない結果を招いている可能性があります。
とはいえ、これを「挑戦的な試み」として評価する視点も重要です。
まとめ
映画「大怪獣のあとしまつ」は、怪獣映画の新たな可能性を示した作品です。
独自のテーマ設定と社会的な視点を取り入れることで、観客に新しい考え方を提案しています。
しかし、エンターテインメント作品としての完成度には課題も残ります。
この作品が観客にとってどのような印象を与えたのか、今後の怪獣映画にどのような影響を及ぼすのか注目されます。
総じて、従来の枠を超える意欲的な一作として評価するに値するでしょう。